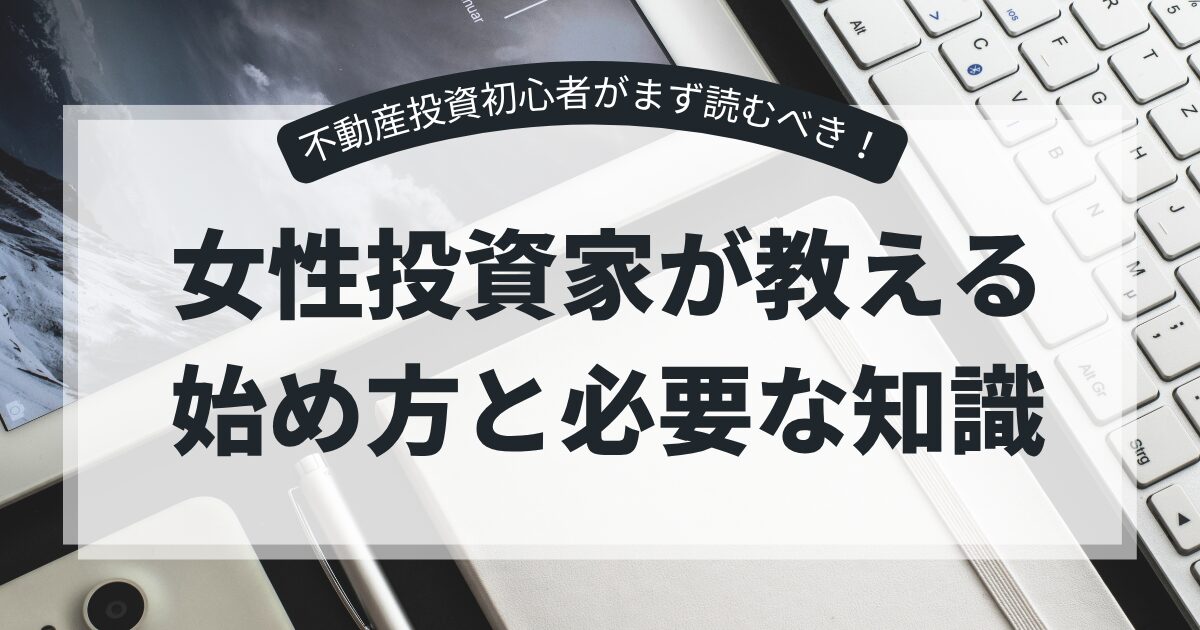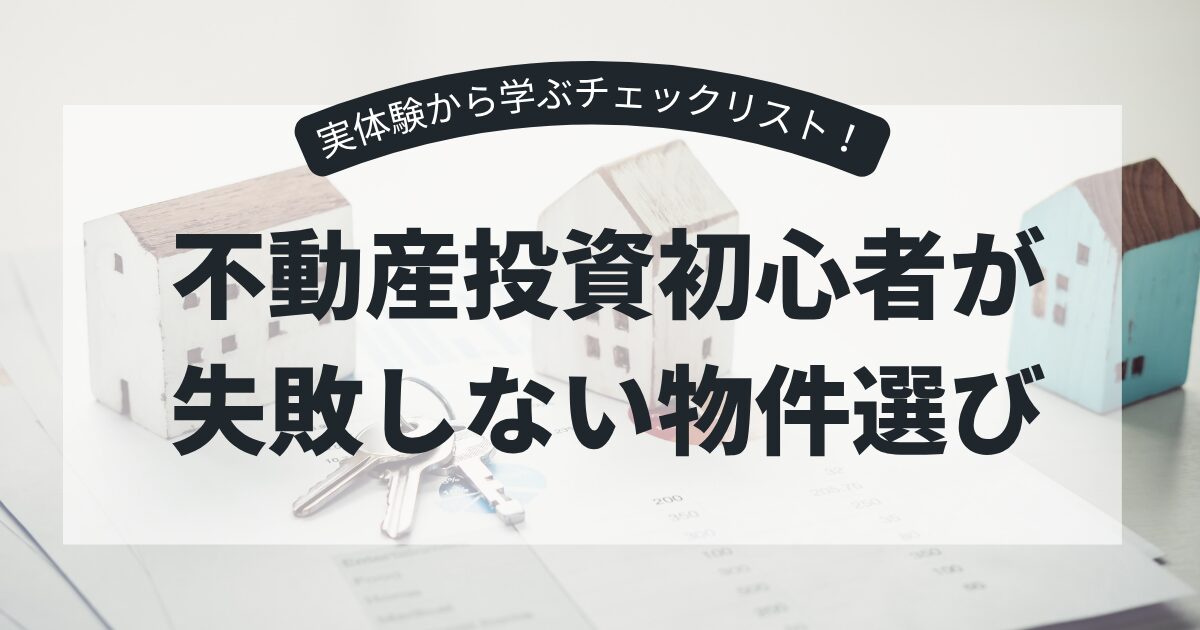私自身、最初の不動産投資では「利回り10%」という数字だけを信じ、管理会社選びなどを甘く見て痛手を負いました。
修繕積立金の値上がりや売却戦略の欠如など、想定外の問題が次々と発生し、初心者だからこそ避けられない失敗も経験しました。
この記事では、私が実際に体験した5つの失敗と、その過程で得たリアルな学びを赤裸々にお伝えします。
これから不動産投資を始める方が同じ過ちを避けられるよう、具体的な事例と改善策をまとめました。
ぜひ最後まで読んで、失敗を回避する参考にしてください。
最初に購入した築古区分マンション3室の話です。
① 利回りだけを見て物件を選んでしまった

最初の物件選びで、私は「表面利回り10%」という数字だけを見て購入を決めてしまいました。
しかし実際に運用してみると、修繕費・管理費・固定資産税などのランニングコストが予想以上にかかり、実質利回りは7%程度でした。
当時は毎月1万円程度のおこづかいが入ってきていたので満足していましたが、
築古区分マンションで7%ぐらいだと今考えると少ないな…というのが所感です。
特に区分マンションの場合、修繕積立金が上がるリスクや、管理費の見直しもあるため、「利回りだけで判断するのは危険」だと痛感しました。
初心者ほど、表面上の利回りに惑わされやすいので注意が必要です。
学び:「利回り10%」という数字の裏には必ず理由がある。管理費・修繕積立金・入居需要をすべて確認してから判断すること。
②修繕積立金の値上げでキャッシュフロー崩壊

①と似ている内容となります。
3つめのの区分投資物件は、銀行ローンの返済額と想定家賃をざっくり計算して「なんとか回る」と判断して購入しました。
しかし、実際に運用を始めてみると、思わぬ支出が次々に発生。
共用部分の修繕積立金が購入後にいきなり月5,000円アップ。
管理組合の決定だったため、オーナーとしては避けられず、毎月のキャッシュフローが一気に悪化しました。
さらに、購入してすぐに、入退去があり原状回復費や、玄関ドアなどの小修繕も重なり、「黒字のはずが実際は赤字」という状態に。
5年保有することでなんとかプラスマイナスゼロ程度にもっていくことができましたが、厳しい運営内容でした。
不動産投資は「購入時の返済シミュレーション」だけでは不十分。
「将来的に上がる可能性のある費用(管理費・修繕積立金・固定資産税)」まで見込む必要があると痛感しました。
💡学びポイント
-
修繕積立金は購入後に値上がりするケースが多い。
→ 管理組合の過去議事録や長期修繕計画をチェックすべき。 -
キャッシュフローは「最悪シナリオ」でシミュレーション。
→ 空室3ヶ月・支出+1万円/月でも耐えられる余裕が必要。 -
「ローン返済=完結」ではなく、維持費・修繕費も毎月積立てておくこと。
③ 管理会社選びに失敗した
初めての不動産投資で、オーナー交流会が行われていて、他にも満足しているオーナーがたくさんいるから安心だと思い、
深く調べずに、購入した会社に物件の管理も任せてしまいました。
最初はこじんまりとした会社で顧客や管理戸数も多くなく、空室対策もしっかりしてくださいました。
ところが、途中から会社が大きくなるにつれて、素人同然の社員が電話をしてきたり、
入居者対応が遅かったり、クレーム処理にも時間がかかり、オーナーとしてモヤモヤすることが多発。
別の会社で売却依頼することに決めてから慌てて幹部の人から電話が入りましたが、時すでに遅しでした。
学び:管理会社は「現場対応力」で選ぶ。納得がいかなければ変更も検討しよう。
実際に担当者と会い、対応の速さ・提案力・入居者対応の丁寧さを見極めることが重要です。
④ 売却戦略を持たずに購入してしまった
私が最も後悔した失敗のひとつが、「売却戦略を考えずに購入してしまったこと」です。
当時は保有していてローンがなくなったら、不動産がキャッシュマシーンにかわると信じていて売却のことなんて頭からすっかり抜けていました。
購入から8年後、東京の物件価格は全体的に上昇傾向にありました。
ニュースでも「不動産バブル」「資産価値の高騰」などと騒がれていますが、私の保有していた単身者向けの築古区分マンションは、思ったように値上がりしませんでした。
残債はすでになかったものの、売却査定をしてみると購入時とほぼトントン。
周辺相場が上がっているにも関わらず、自分の物件はなかなか価格が伸びなかったのです。
単身用区分マンションは「投資家しか買わない」現実
理由を分析してみると、単身者向け区分マンションは「自分で住みたい人」が少なく、ほとんどが投資家同士の売買。
そのため、実需(住む人)による需要が薄く、価格の上昇余地が限られていました。
投資家はお得感がないと買ってくれません。
つまり、「利回りが下がれば買い手が減る」「築年数が古くなると価値が落ちやすい」という構造的な弱点があったのです。
そのことを理解せず、出口(売却)を想定せずに購入していた自分の甘さを痛感しました。
また、管理費や修繕積立金があがったことにより利回りが購入当時より下がっていたので値段が伸びない要因となりました。
出口戦略を持たない投資は“ゴールのないマラソン”
不動産投資は「買って終わり」ではなく、「売って完結」するものです。
購入前に、「いつ」「誰に」「いくらで」売る可能性があるのかを想定しておかないと、好調な市況でもチャンスを逃してしまいます。
学び:
・出口戦略は購入時点で考えておく
・実需のあるエリア・間取りかどうかを確認する
・複数の不動産会社に査定を依頼して、売却時の“想定ライン”を把握しておく
今では、物件を購入する前に「出口価格」と「想定利回り」をセットでシミュレーションし、売却益も含めた総合的なリターンを考えるようにしています。
この経験は、私の投資判断の精度を大きく上げてくれました。
まとめ:失敗からしか学べない“不動産投資のリアル”
不動産投資初心者が陥りやすい失敗には、利回りだけで物件を選ぶこと、管理会社選びの失敗、“利回り10%”に釣られた区分マンション購入、売却戦略なしの購入があります。
私も同じ失敗を経験し、そこで得た教訓は「実質利回りの把握」「信頼できる管理会社選び」「修繕積立金の確認」「明確な出口戦略」です。
不動産投資は初心者にとって失敗の連続かもしれませんが、事前準備と学びを積み重ねることで成功の確率は飛躍的に上がります。
もしこれから不動産投資を始める方がいるなら、「失敗を避けるために他人の失敗から学ぶ」ことをおすすめします。
▶関連記事
-

-
不動産投資初心者がまず読むべき!女性投資家が教える始め方と必要な知識まとめ
2025/10/2
-

-
不動産投資初心者が失敗しない物件選び|実体験から学ぶチェックリスト
2025/10/1